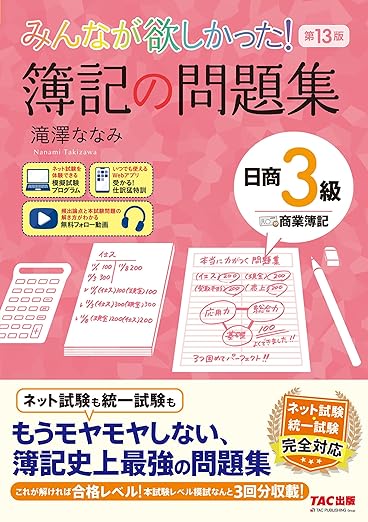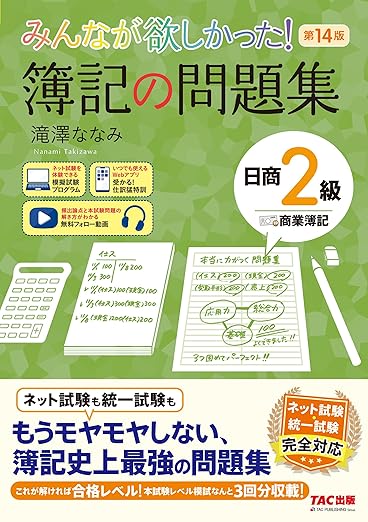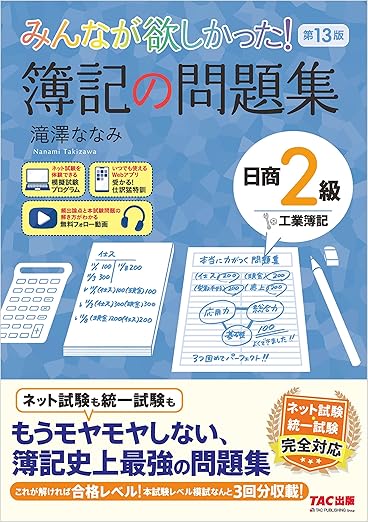久しぶりにブログを更新してみます。
新卒の会社で少し触れて以来、簿記や会計に取り組むことはなかったのですが、「知っておかないとダメだな」思ったので、一念発起してしっかり学んでみることにしました。
簿記とは
日本商工会議所のHP では以下のように書かれています。
簿記は、企業規模の大小や業種、業態を問わずに、日々の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。
簿記を理解することによって、企業の経理事務に必要な会計知識だけではなく、財務諸表を読む力、基礎的な経営管理や分析力が身につきます。また、ビジネスの基本であるコスト感覚も身につきますので、コストを意識した仕事ができるとともに、取引先の経営状況を把握できるために、経理担当者だけではなく、全ての社会人に役立ちます。さらに、公認会計士や税理士等の国家資格を目指す方や他の資格・検定と組み合わせてキャリアアップを考えている方々にも必須の資格といえます。
「財務諸表を読む力、基礎的な経営管理や分析力」も身につくようです。
なぜ簿記を勉強しようと思ったか
「財務諸表をもう少し読めるようになりたい」と思ったのがきっかけです。
普段はソフトウェアエンジニアとして働いているので、基本的には経理や財務の仕事はしないのですが、4年前に会社を創業したこともあり、ビジネスや経営についても考えたり調べたりする機会が増えていました。
自然と他社の財務諸表を見ることも増え、もちろん自社の財務諸表と向き合う必要もあり、だましだましやっていましたが、「もう少し体系的にやろう」と思って、今回は日商簿記の2級に取り組むことにしました。
また、新卒の時に一度、簿記を受けようと思って挫折していたことも影響したかもしれません。時間があった時に勉強を始めたのですが、少し忙しくなったタイミングで勉強をやめてしまっていました。
今回は時間がかかることを理解したうえで、腰を据えて取り組むことにしました。
なぜ実際に試験を受けようと思ったか
「簿記2級」という資格が欲しいわけではなかったのですが、
体系的に学びたい
理解が怪しい状態のまま終わりたくない
と思ったので、実際に試験を受けて合格することを目標にしました。
そのため、
「合格点を取るための勉強」というよりは「試験範囲全体を網羅的に勉強」
「なんとなく理解した状態」ではなく「試験で点数をしっかり取れるくらい理解した状態」
となるよう気をつけて進めました。
勉強の進め方
まず、簿記3級 を受験して、その後で 簿記2級 を受験しようと考えました。
3級は2級の基礎となっているようだったので、学習効率が良さそうかなと思ったのと、簿記検定自体があわなそうであれば、3級の時点でやめてしまおうと考えたためです。
結果的に3級の勉強が面白かったので、そのまま2級へと進みました。
簿記3級への取り組み
簿記3級の概要
簿記3級の試験では、基本的な商業簿記の知識が問われます。「商業簿記」とは、主に商品の売買やサービス提供に関する取引を記録する簿記のことです。企業の財務状況や経営成績を外部に報告するために使用され、特に小売業やサービス業で用いられます。
※ 2級で出てくる「工業簿記」は製造業における原価計算や製品コストの管理を目的とした簿記を指します。
3級では、初歩的な実務がある程度できるようになり、小規模企業の経理事務の業務をこなせる程度の知識が要求されます。
試験内容と形式
試験内容は以下の通りです。
設問 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
第1問 | 仕訳問題 | 45点 |
第2問 | 帳簿記入 | 20点 |
第3問 | 決算整理絡みの総合問題 | 35点 |
試験時間は60分、100点満点で70点以上が合格となります。
サンプル問題も 日本商工会議所のHP から確認可能です。
CBT方式の受験(ネット試験)が可能で、全国にある試験会場から日程を選んで受験できます。
どう勉強したか
メインの勉強としては ふくしままさゆき さんのYouTubeで学ばせていただきました。
解説がしっかりしていてわかりやすく、納得感を持ちながら進めていくことができました。
簿記3級のプレイリストは全部で26本動画があり、合計で15〜20時間程度の長さかと思います。自分の場合は基本2倍速で視聴し、わからないところはスピードを遅くしたり、一時停止したりして、理解しながら進めていきました。演習問題もたくさんあり、2周するとかなり理解が深まった感覚がありました。
また、試験形式に慣れるために、以下の問題集で模試を3回分解きました。本当は模試以外の問題についても解けばよかったのですが、ふくしまさんのYouTubeでかなり理解を深められていそうだったので、模試以外の問題はほとんど解かずに試験に臨みました。
総勉強時間としては30時間くらいかと思います。
87点で無事に合格できました。
簿記2級への取り組み
簿記2級の概要
簿記2級の試験科目は商業簿記と工業簿記になります。
「商業簿記」は3級の内容に比べ、より広く高度になります。具体的には、3級で学んだ商品売買・固定資産などをさらに幅広く学習するとともに、中小企業の会計処理を学習します。具体的にはリース会計、為替取引、連結会計、税効果会計などの学習があげられます。
「工業簿記」では、製造業における原価計算全体の流れを学習し、注文を受けてから製品の製造にかかる個別原価計算や、企画品製造にかかる総合原価計算を学習します。また、実際の製造活動が目標通り行われているかをチェックする標準原価計算や、短期的な利益計画と結びつく直接原価計算などを学習します。
試験内容
試験内容は以下の通りです。
設問 | カテゴリ | 内容 | 配点 |
|---|---|---|---|
第1問 | 商業簿記 | 仕訳問題 | 20点 |
第2問 | 商業簿記 | 特定分野の個別問題 | 20点 |
第3問 | 商業簿記 | 決算整理絡みの総合問題 | 20点 |
第4問 | 工業簿記 | 仕訳問題 | 28点 |
第5問 | 工業簿記 | 各種原価計算 など | 12点 |
試験時間は90分、100点満点で70点以上が合格となります。第2問と第3問は仕訳をしっかり作った上で勘定を記入したり、財務諸表を作ったりするので、重い問題が多いです。
サンプル問題も 日本商工会議所のHP から確認可能です。
3級と同様、CBT方式の受験(ネット試験)が可能で、全国にある試験会場から日程を選んで受験できます。
どう勉強したか
2級でも、まずは ふくしままさゆき さんのYouTubeで勉強を進めました。
商業簿記(全35回)・連結会計(全10回)・工業簿記(全35回)のプレイリストを視聴して理解を深めていきました。合計で商業簿記が25〜30時間、連結会計が5〜10時間、工業簿記が25〜30時間程度の長さかと思います。
2級と同じく基本2倍速で視聴し、わからないところはスピードを遅くしたり、一時停止したりして、理解しながら進めていきました。まず2周して全体の理解を深めた後、理解の怪しいところは3周目も視聴しました。
続いて2級でも問題集を解くことにしました。3級で使ったのと同じ「みんなが欲しかったシリーズ」のものを使いました。商業簿記・工業簿記とそれぞれ別の問題集になるので以下の2冊に取り組みました(問題集以外に 教科書 も2冊あるのですが、そちらは使っていません)。
3級の時は模試を解くだけでしたが、2級では対策問題も模試もあわせて解きました。
対策問題は最初に1周解いた後、2周目は間違えた問題だけを解き、そこで間違えたものはさらに3周目で解き直しました。
模試も6回分あったので、全て解いた後、間違えたところを解き直しました。
YouTubeで75時間程度、問題集で75時間程度、合計約150時間の勉強を行いました。はじめに気をつけようと思っていた「試験範囲全体を網羅的に勉強」と「試験で点数をしっかり取れるくらい理解した状態」のどちらも達成したかなと思ったので、試験を受けに行きました。
試験
勉強はしっかりやったものの、少し緊張しながら試験を受けに行きました。
結果は98点。第2問が比較的簡単な株主資本等変動計算書の問題だったので、少し拍子抜けしましたが、無事に合格できてよかったです。
満点だったらより良かったですが、網羅的にしっかり理解できてることが確認できたので、良い結果を出せたと思います。
振り返り
学習前とどう変わったか
感覚的ですが、財務諸表と少し仲良くなれそうな気がしています。これまでIR情報というと、決算説明資料のスライドを読むことがほとんどだったのですが、決算短信や有価証券報告書も見て、財務諸表もしっかり確認しようという気持ちになれました。
もちろん知らない言葉もたくさんありますが、学習前と比べると知っている言葉も増え、少し馴染みのあるものになったなと感じます。
また、自社の話で言っても、財務諸表に対する理解はとても深まったなと思います。また、各種の個別元帳も見方がわかりました。法人税や消費税の中間納付も勉強したので、「もう少し早く勉強しても良かったな...」と感じました。
良かったところ
今回は全体的にとても効率よく学習できた気がします。以前挫折した時を思い出しながら、何が改善されたのか考えながら書いてみます。
良い教材に出会えた
ふくしままさゆき さんのYouTubeで勉強できたのが、とても大きかったと思います。
最初に学習方法を調べた時に、Google検索やYouTube検索で探す中で見つけたのですが、理論を詳しく解説していただいていて、しっかり理解しながら進めたい自分にはぴったりでした。
かつては本を買って進めようとした記憶がありますが、その時よりだいぶわかりやすく学習できた気がします。
YouTubeだとスキマ時間に勉強しやすい
メインの学習としてYouTubeを視聴していたため、電車に乗っている時間やちょっとした待ち時間でも簡単に勉強を進めることができました。
ノートとペンが必要だったり、物理本が必要だったりする場合と比べて、とべも勉強しやすかったなと思います。
また、YouTubeでは倍速視聴もできるため、比較的自分のペースで進めやすいのかなと思いました。
必要な時間を予測して確保する
簿記2級はなかなか範囲が広いので、(自分の場合は少し短い時間で終わりましたが)一般的に必要な勉強時間は250〜350時間ともされるようです。1日3時間でも3ヶ月かかると考えると大変ですよね。
以前の自分も、必要な時間を考えずにとりあえず始めて、忙しくなったタイミングで全然時間が取れなくなって挫折していました。
今回は、勉強を始める前にちゃんと必要な時間を想定して、未来のスケジュールを予測した上で、時間が取れそうなタイミングで始めることができました。また学習を進めていく中で、予定通り進められそうか、今のペースだとどのくらいに終わりそうか確認しながら進められたことも良かったです。
終わりに
合計で180時間ほど勉強したので、なかなか大変でしたが、思っていたより簿記は面白く、終始楽しく学べました。社会人経験を重ねたことにより、新卒の時に興味を持てなかったような内容が、少し身近に感じられたことも大きかったのかもしれません。
無事に合格できてもちろん良かったのですが、本来の目的は「財務諸表をしっかり読む」ということなので、今回得られた知識を活かしながら、たくさん財務諸表を読んで、自分の考えも深めていけたらと思います。
Share this post